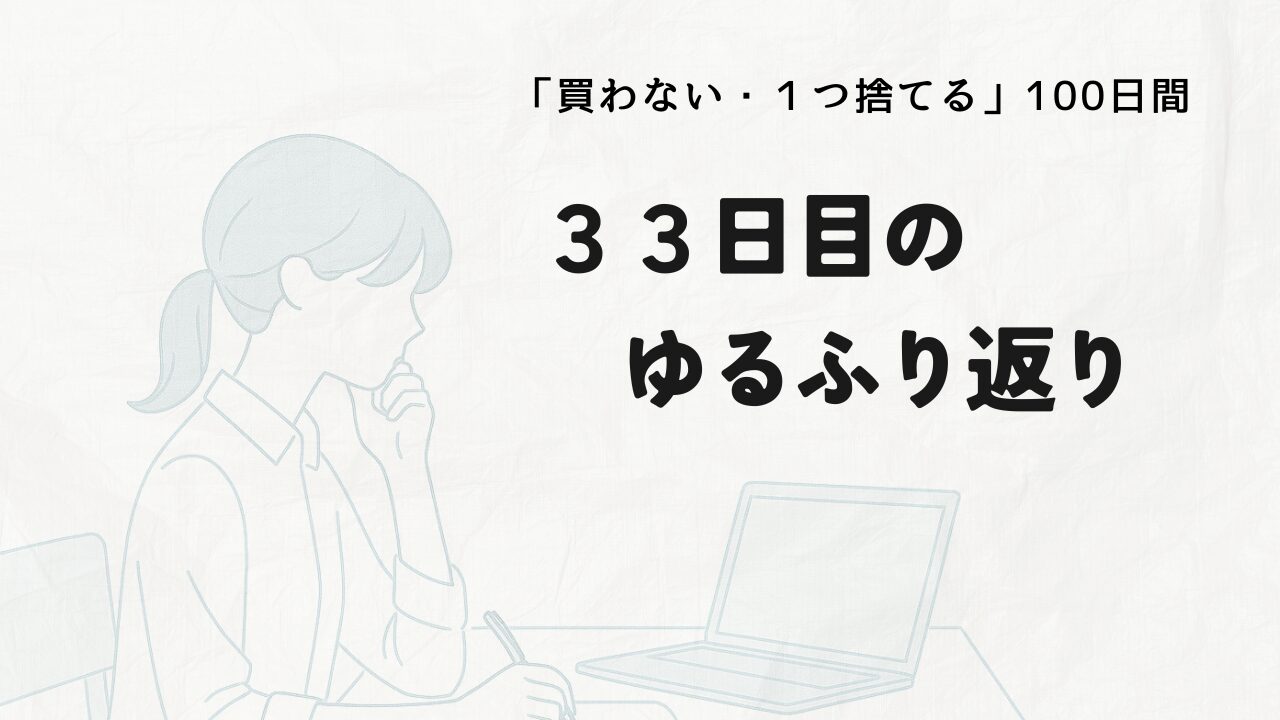「捨てる100日」をスタートして約1ヶ月が過ぎました。
こうして毎日自分が所有しているモノと向き合うといろんなことが見えてくるもの。
今日は捨てる33日間を振り返って気づいたことなどについて。

日々ひとつずつ捨てていく中で、ふと気づいたことがある。
「あれ?最近、ものが増えていない」
もちろん意識的に「買わない」と決めているのもあるけれど、
それ以上に、“買う”という行為そのものが、自分の中で前よりずっと慎重になっている気がする。
特にこの100日間は「生活用品以外は買わない」とルールを決めていて、
毎日“捨てる”ことと向き合っているからこそ、「本当に必要?」と立ち止まるクセがついてきた。
以前なら、気になったらとりあえず買っていたような場面で、今は自然とスルーできている。
そして改めて気づいたのが——
私の中で“100円ショップ”が、かなりものを増やす原因になっていたということ。
SNSで新商品や便利グッズの情報を見ると、「これ、使ってみたいな」とすぐに買いに行きたくなる。
実際、週に何度も足を運んでいた時期もありました。
でも、この「捨てる100日」を始めてから行ったのは、消耗品を買いに1度だけ。
あれだけ頻繁に通っていたのに、行かなくなった今も特に困っていないことに驚いている。
確かに便利なアイテムも多いけど、よくよく考えてみれば、
「プラスアルファの便利さ」であって、「絶対必要!」というものではない。
しかも、うまく使いこなせなかったり、失敗して放置してしまうことも少なくなかった。
100円だから気軽に買えるし、ダメでも気軽に捨てられる——そう思っていたけれど、
いざ“捨てる”となると、「もったいないな」とか「罪悪感あるな」といった感情がついてくる。
そのストレスがいやでつい後回しにしていた結果、気づけばものが増えていたんだなぁと。
捨てることを続けていく中で、「増やさない意識」が自然と育ってきたこと。
それがこの33日間で、いちばんの変化かもしれない。