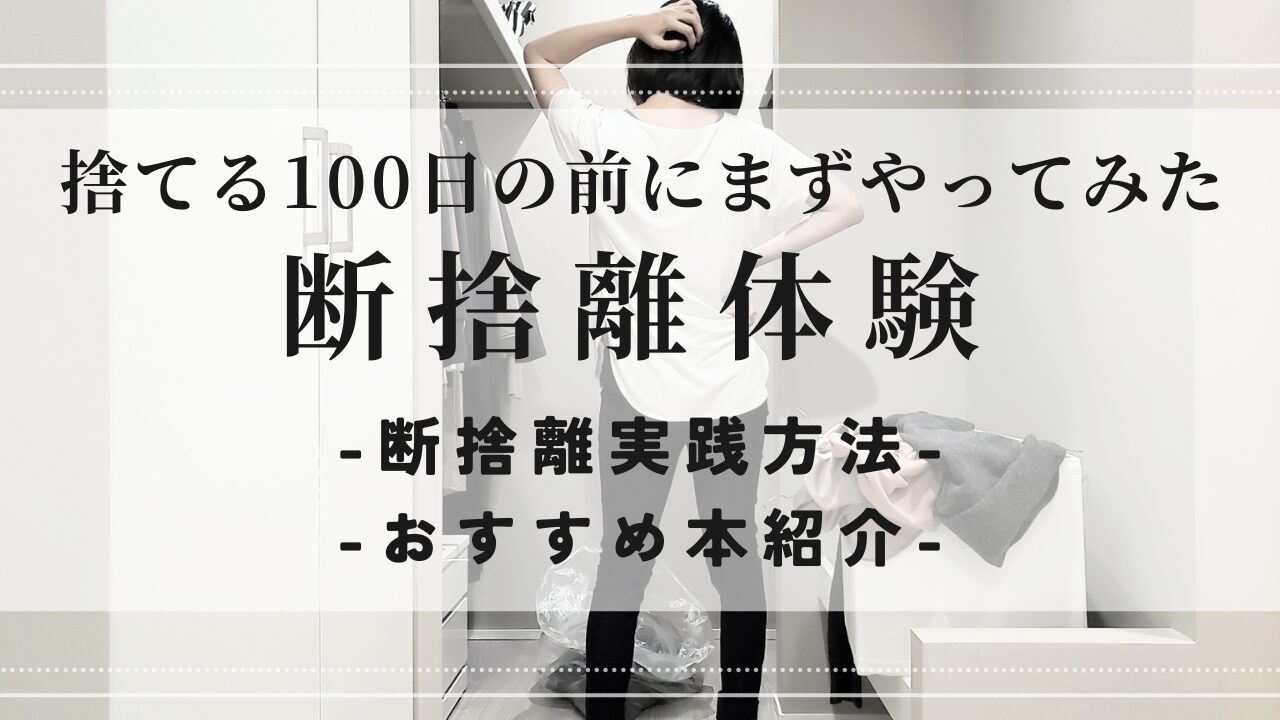「捨てる100日」を始めるの前の断捨離実体験と役に立ったおすすめ本を紹介します
断捨離の火がついた日|始まりはクローゼットの衣類カバーだった

「整理整頓、したつもりだけど、気がついたらまたモノであふれている」
「断捨離、したいけど、何から手をつけたらいいか分からない」
そんな思いを、抱えていました。
モノは多い。使ってないものもある。だけど全部いきなり捨てるのは怖いし、
もったいない気もする――。
そんなモヤモヤを抱えながらも、ある日ふとしたきっかけで断捨離を始めました。
それは、「衣類カバー」を取り替えようとしただけの、ほんの小さな出来事でした。
これまで、クリーニングから戻ってきた衣類についているビニールカバーを使用していましたが、
家庭での長期保管には適していないと聞き、入れ替えることにしました。
100円ショップで買った30枚の通気性カバーが、クローゼットで一瞬で消えていったとき。
私は初めて、自分がどれほど服を持っていたのかに気づいて、
目が覚めたような気持ちになりました。
30枚で足りない? まさかそんなに服を持っていたなんて……
呆然としました。
自分が思っていた枚数と実際の所持数の差に驚愕したのを覚えています。
このとき初めて、「自分は“服を持ちすぎていた”ことに無自覚だった」と気づいたのです。
その気づきが、私の断捨離の火をつけました。
この記事では、「捨てる100日」を始める前の、断捨離について。
自分に合った“断捨離”の始め方や、気をつけたいポイントも紹介するので、
「何から始めたらいい?」という方のヒントになればうれしいです。
実践した断捨離のやり方|“音声で聞く片づけセラピーのように”オーディブル断捨離

本格的に断捨離を始めた私は、ひとつルールを決めました。
「集中できる環境をつくること」と「楽しさを感じながらやること」です。
そのために取り入れたのが、Audible(オーディブル)。
\今なら初月無料で本が聴き放題/
Audible無料体験はこちら作業中、常にイヤホンで断捨離に関する本を流していました。
手は無心にモノを仕分けしながら、耳では“片づけの教え”を聴く――
耳から流れる言葉に意識を傾けながら、瞑想するように無心で断捨離していたのを覚えています。
人によって正解が違う断捨離。
だからこそ、いろんな著者の本を聴いて「いいとこ取り」をすることで、
自分に合ったやり方を自然と見つけていけた気がします。
📕オーディブルで聴いて参考になった本
▶︎ Audibleは無料体験できます:
Audible無料体験はこちら捨てる決意を後押ししてくれた、最強の“開運マインド”の本

モノを一気に“全捨離”することで、運気が上がる。開運と片づけが密接につながっているという、スピリチュアル寄りのアプローチになってます。
「執着を捨てる」「モノを取るか運を取るか」ただ片づけるのではなく、“運”というもっと大きなものと交換するような感覚に気づかされました。
断捨離を頑張りすぎて寝込んだとき、ふとこの本に出てくる「邪気」の仕業かも?と思いました。頭痛がしたり寝込んだりする人がいるそうですが、納得です。
空間づくりの大切さにハッとする。手が止まったときに後押ししてくれた本

家の空間がどれだけ運を引き寄せるかに着目し、「不要なモノを手放すこと=人生の流れを変えること」と教えてくれる1冊。
この本を聴いていたことで、断捨離の途中で「ただ捨てるだけじゃなく、人生全体を整えることにつながっている」と意識できるようになりました。
「この作業の先に、どんな未来が待っているのか?」――そんな効果を思い描きながら進めることで、作業に前向きな気持ちで取り組めたのを覚えています。
本当に必要なものは何か?ゼロベース思考で前向きになれる本

減らすことだけでなく、「自分にとって本当に大切なものを増やす」という新しい視点のミニマリズム。
「何もないところから、1日ずつモノを増やしていく」——この考え方に、新しい暮らしの可能性を感じました。
次は何を選ぶんだろう?とワクワクしながら聴いていたのを覚えています。
本当に必要なモノは何かに気づかせてくれて、「迷ったら捨てる」背中を押してくれた1冊。
“捨てる100日”という発想のヒントも、この本から得たのかもしれません。
作業の手が止まるほど参考に。リアルなアイテム選びのヒントをくれる本

月10万円でも心豊かに暮らすための「生活の知恵」。暮らし全体を見直すヒントが詰まっています。
生活をシンプルにするアイテムがとても参考になりました。
正直、すぐに検索したくなって手が止まることもしばしば(笑)。
でも、それだけリアルで具体的なアイデアが詰まっていて、断捨離中のモチベ維持に役立ちました。
捨てないリスクに気づく。断捨離中のモチベ維持に役立った本

上記の「整理術」と対になるような本。日々の生活の“しくみ”を整えて、自分に合ったシンプルライフを追求するための実践アイデアが満載です。
この本を通して、「いらないモノのために、多くのモノや時間を失っていた」と気づかされました。
ただ整理するのではなく、“選び取る生活”の大切さに目が開かれた感覚です。
捨てなかったことで失っていた時間や空間に気づき、リスクを実感したことで断捨離が一気に進みました。
「ときめくか?」の問いかけで、迷いがスッと晴れた。楽しく作業が進む本

世界的ベストセラーとなった「ときめき」を基準にした片づけ術。物を一つひとつ手に取り、“ときめくかどうか”で残すか手放すかを判断する独自の方法は、単なる整理整頓ではなく、人生の再構築にもつながるとされています。
丁寧な捨て方のアドバイスがとても実践的でした。
オーディブルの語り口が明るく楽しく、作業中の気持ちを軽くしてくれて、断捨離の良い相棒になってくれました。
立ち止まりそうなときに読むと、手がまた動き出す本

スピード感を持って「捨てたい!」と思っている人向けの片づけ術。優先順位のつけ方や、考えすぎずに行動するコツが明快に解説されています。
捨てられないいくつもの落とし穴について解説されていて、断捨離の途中で手が止まりそうになったときも、何度も背中を押してもらえました。
作業の終盤、心まで整う時間をくれた本

禅の思想をベースに、「手放すこと」の精神的な意味を静かに語る一冊。物だけでなく感情や執着の整理についても深い気づきを与えてくれます。
断捨離の終盤に聴いて、沸騰しそうだった頭がまるで浄化されていくような感覚を覚えました。
心が静まる時間を作りたい方におすすめです。
▶︎有効的に捨てたい方はこちら
やってみて気づいた、注意しておきたいこと

断捨離を一気にやるのはキケン。
私は断捨離を甘く見て寝込んでしまいました。
断捨離は「モノを捨てるだけ」と思い、やる気が出たある日、無双状態に突入。
1日中、部屋中を片っ端から整理して、ゴミ袋を何袋も出しました。
捨てる手が止まらない。
気持ちが乗ってくると、快感すら覚えるようになって、
「今のうちに全部やってしまいたい」と思ってしまうんです。
でも――翌日。
私は完全にダウンして、ほぼ何もできない状態になってしまいました。
身体が重く、頭も痛くて。。
どうやら知らず知らずのうちに、体力・気力・判断力を使い果たしていたようです。
断捨離って、思った以上にエネルギーを使う作業なんだと身をもって実感しました。
だからこそ、少しずつ、休みながら、マイペースに続けるのが大切。
“今日はこれだけ”と決めておくくらいが、ちょうどいいのかもしれません。
断捨離は「頭を使う有酸素運動」だと思って、無理せず、続けられる形を探すのが◎
「捨てる100日」の背景|捨てきれなかったモノと向き合うために
数日間かけて断捨離に集中したことで、部屋はかなりスッキリしました。
クローゼットも、棚も、引き出しの中も。明らかに「モノが減った」実感はありました。
でも、そのあとふと思ったのです。
「…まだ、捨てられるモノがあるんじゃない?」
一度“断捨離スイッチ”が入ると、目に見える量だけでは満足できなくなってくる。
次に気になってきたのは、「手放さなかったモノ」たちの存在でした。
それは、最初の断捨離では残すと判断したモノたち。
でも本当に、それって“必要だから残した”のか?
それとも、何かの執着で手放せなかっただけなのか?
そんな疑問が浮かんできたとき、思いました。
今すぐ全部を見直すのは無理でも、毎日少しずつ、時間をかけて向き合ってみよう。
そこで始めたのが、「100日間で1日1つずつ、手放す」チャレンジです。
短距離走では気づけなかった“気持ちの引っかかり”を、
長距離ランのようにじっくり見つめていく。
ただ捨てるだけじゃない、“執着との対話”を大事にしていこうと決めました。
この「捨てる100日」の記録が、今ブログで綴っている「捨てる100日」のシリーズです。
最後までお読みいただきありがとうございました。